親知らずの周囲が頻繁に腫れる
親知らずは、部分的に歯肉に覆われた状態で生えたり、歯ブラシが届きにくい場所に生えたりします。清掃が行き届かない場合が多く、トラブルを引き起こしやすいです。親知らずが原因で腫れや痛みが起こるのを智歯周囲炎とよび、幅広い年齢層でみられます。一般的な歯肉の炎症よりも症状が強めに出るケースも少なくありません。また、親知らずやその周りが虫歯や歯周病になっている場合も、抜歯すべきだと診断されます。
歯科口腔外科|国分寺でインプラント治療ならチカワデンタル
口腔外科は、お口の中、顎、顔面などに関する病気や怪我、トラブルを扱う診療科です。困難な親知らずの抜歯をはじめ、顎関節症の治療、歯の移植、歯冠長延長術などをご提供します。症状によっては、より専門的な医療機関をご紹介することもできます。お口周りで気になる症状がありましたら、チカワデンタルの口腔外科を受診ください。

噛み合わせに異常があると、お口だけなく全身の健康にも悪影響を及ぼします。原因がわからない頭痛、首や肩のこりなどは噛み合わせに問題があるのかもしれません。このほかにも、手足のしびれ、腰痛、顎関節の痛み、動悸・息切れ、難聴、めまいなどの不調がみられる場合、噛み合わせ症候群と診断されることがあります。治療では顎のずれを調整し、適切な噛み合わせを目指します。

親知らず(第3大臼歯)は、10代後半から20代にかけて生えてくる、一番奥にある歯です。上下左右に1本ずつ、合計4本生えることがあります。
この歯は、生える向きや位置によって問題を起こすことがあり、場合によっては抜歯が必要になることもあります。たとえば、斜めに生えて隣の歯を押したり、歯肉の中で炎症を起こしたりするケースです。
ただし、親知らずは必ず抜く必要があるわけではありません。まっすぐきれいに生えていて、問題がなければ、将来別の歯の代わりとして使えることもあるため、残しておいた方が良い場合もあります。
親知らずは、部分的に歯肉に覆われた状態で生えたり、歯ブラシが届きにくい場所に生えたりします。清掃が行き届かない場合が多く、トラブルを引き起こしやすいです。親知らずが原因で腫れや痛みが起こるのを智歯周囲炎とよび、幅広い年齢層でみられます。一般的な歯肉の炎症よりも症状が強めに出るケースも少なくありません。また、親知らずやその周りが虫歯や歯周病になっている場合も、抜歯すべきだと診断されます。
親知らずが真っ直ぐに生えておらず、横や斜めに生えていたり、横に倒れて歯肉に埋まっていたりすると汚れを取り除きにくく、虫歯や歯周病を起こす原因となります。
親知らずが原因で形成された深いポケットは、親知らずを抜かない限り、悪化してしまいます。
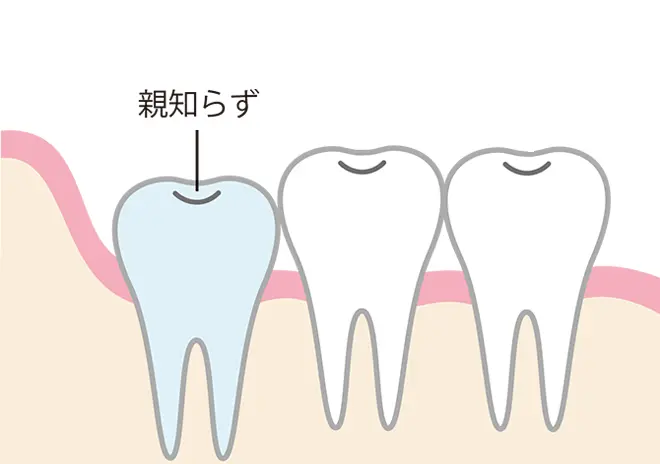
親知らずがまっすぐ生え、上下の歯としっかり噛み合っており、日常生活に支障がなければ、抜歯の必要はありません。

親知らずに炎症や虫歯、歯周病がなく、清潔に保たれていて今後もリスクが低いと判断されれば、経過観察が可能です。

親知らずが深く埋まっており、ほかの歯に影響せず痛みもない場合は、あえて抜歯せず経過観察となることがあります。

親知らずが正しい位置に生えていて、ほかの歯としっかり噛み合っている場合は、咀嚼(そしゃく)機能を助けるだけでなく、将来的にブリッジや歯の移植に使える可能性もあります。
たとえば、大臼歯(奥歯)をやむを得ず抜かなければならなくなったとき、自分の親知らずをその位置に移植できることがあります。自分の歯なので馴染みがよく、自然な仕上がりになります。
また、大臼歯を失った際に親知らずが残っていれば、入れ歯の支えやブリッジの土台としても役立ちます。
当院では以下の流れで親知らずの治療を進めていきます。
基本的には1回目の受診時に初期診療を行ない、2回目以降に治療を開始します。急を要する場合は柔軟に対応します。
診察・カウンセリングの後、レントゲン撮影で歯の状態を詳しく確認します。これらをもとに、患者様に合わせた治療計画を立てます。
治療に関して丁寧に説明を行ないます。患者様に充分にご納得いただいてから親知らずを抜歯し、歯肉を縫合します。
歯肉に縫い合わせた糸を取ります。また、周りの歯が虫歯や歯周病にならないように歯磨き指導を行ないます。
親知らずの抜歯は多くの患者様が悩むものです。抜かなくてもいいケースもあれば、放っておくとお口のトラブルの原因になるケースもあります。ご自身の親知らずがどのような状態なのかを知るために、私たちにぜひご相談ください。

顎関節症になると、顎が痛む、口が大きくあかない、顎関節から音が鳴るといった症状が現れます。治療では、専用に型取りをしたマウスピースを装着していただき、徐々に症状の緩和を目指します。マウスピースを用いた治療は保険診療です。
なお、顎関節の骨の病気や、関節円板周囲の組織にダメージがある場合などは、より専門的な治療や手術が受けられる医療機関へのご紹介も行なっています。
・「顎が痛む(顎関節痛・咀嚼筋痛)」
・「口があかない(開口障害)」
・「顎を動かすと音がする(顎関節雑音)」
の3つです。そのため、硬い食べ物が噛めない、大きな物が食べにくい、顎の音が気になるといった問題が生じる可能性があります。
噛み合わせの改善が一般的な治療法になります。例えば、スプリント(マウスピースのような装置)を上顎あるいは下顎に入れ、上下の歯が均等に接するように治療します。これにより顎関節が正しい位置となり、筋肉の緊張が和らいでスムーズにお口を動かせるようになります。
重症の場合は手術を実施する可能性もありますが、患者様一人ひとりの症状によって治療法はさまざまです。気になる症状がある方はまずは当院にご相談ください。以下、具体的な治療法をご紹介します。
消炎鎮痛薬や筋弛緩剤などによる薬物療法で、顎関節の痛みを軽減します。
上顎や下顎にスプリントを装着し、噛み合わせを調整します。顎関節の安静を図ったりずれを修正したりします。

顎関節や咀嚼筋への負担を減らすために、横を向いてテレビを見ない、頬杖をやめる、猫背をやめるといった点を心がけてください。また、生活を送るなかで上下の歯が接触していることに気付いたら歯を離しましょう。そして、強い心理的な緊張を感じる環境があれば、それを改善したり避けたりして、可能な限りストレスをコントロールするのが重要です。

一般的に歯の欠損は、事故や病気などが原因で引き起こされます。歯の移植とは、自分の歯が欠損している場合にほかの箇所から取り出した歯を移植する治療法です。例えば、親知らずを取り出して移植する場合もあります。
歯の移植は1970年以降、研究により有効性が示された治療法で、歯を保持するための歯肉の状態が良好な場合に行なわれます。歯肉の状態が悪い場合は、歯周病などの治療を終えてから移植を行ないます。
失った歯を補う治療法としては、インプラント治療、ブリッジ治療、入れ歯治療などがあります。
歯の移植は、隣にある歯、または抜歯された歯を使用可能です。移植された歯は安定するのに時間がかかるため、移植直後には食事を控え、経過観察が必要です。移植後は感染対策として歯根の治療も行なわれ、それにともなって被せ物も作製します。
歯の移植は歯の欠損を補うだけでなく、歯並びを整えたり噛み合わせの問題を改善したりするためにも行なわれます。ただし、歯の移植には手術が必要なため、適切な評価と治療計画が欠かせません。移植歯の生存率(寿命)は、術後10年で約80%です。

歯冠長延長術とは、外科手術によって歯肉を切開したり歯槽骨(歯を支える骨)を削ったりして、歯冠(歯の目に見える部分)を延長させる治療法です。クラウンレングスニングともいいます。歯肉の位置を下げられるため、笑った時に歯肉が見えすぎてしまうガミースマイルの改善も図れます。また、歯肉に覆われた虫歯や歯の割れなどの治療にも適用可能です。
歯冠が短いと、歯並びが悪く見えたり歯肉とのバランスが悪く見えたりと、審美性の低下を招く場合があります。歯冠長延長術によって歯を長く見せることで、美しい口元を実現可能です。
歯冠が短いと噛み合わせの悪化を招き、歯周病のリスクが高まる場合があります。歯冠長延長術を行なうと、噛み合わせの改善や歯周病予防などの機能的なメリットがあります。
歯周病や歯周外科に関する専門的な知識と技術をもつ歯科医師が行います。
お口の状態や治療の目的に合わせて、適切な診断と治療計画を立てたうえで進めていきます。
症状によっては、歯を残すことが難しいケースもありますが、できるかぎりご希望に沿った方法をご提案いたします。
気になることがありましたら、お気軽にご相談ください。
・症状や治療内容によっては保険を適用できますが、機能性や審美性を重視するため、基本的には自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。
・手術後、歯肉・顎などの炎症・疼痛・腫れ、組織治癒の遅延などが現れることがあります。
・手術後、薬剤の服用により眠気、めまい、吐き気などの副作用が現れることがあります。
・治療内容によっては自費(保険適用外)となることもあり、保険診療よりも高額になります。
・抜歯後の数日は、腫れや痛み、出血が止まらないことがありますが、多くの場合、数日から1週間ほどでおさまります。
・下唇から下がしびれる神経麻痺を生じることがあります。
・舌の一部または全部の神経が麻痺し、味覚も麻痺する場合があります。
・下顎を抜歯した場合、抜歯した傷口から空気が入り、突然頬や顎が腫れることがあります。
・治療内容によっては自費(保険適用外)となることもあり、保険診療よりも高額になります。
・薬物療法で鎮痛消炎剤や筋弛緩剤を使う場合、胃腸障害、眠気、倦怠感などを引き起こすことがあります。
・スプリント治療やプレート治療を行なう場合、装着を怠ると治療期間が長引くことがあります。
・顎関節症は矯正治療により改善されることもありますが、矯正治療と関係なく悪化することもあります。矯正治療を行なったからといって、必ず顎関節症が治るというわけではありません。現段階で、顎関節症と矯正治療との明確な因果関係は示されていません。
・大きく露出した歯根は以前より虫歯や歯周病になるリスクも高まります。(被せる処置で改善できます)
・術後は歯間ブラシを用いるなど、より丁寧な歯磨きが求められます。
・充分な治療期間が必要です。時間をかけて歯肉の回復を待ってから被せる処置を行ないます。